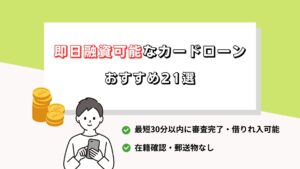「生活福祉資金貸付制度でお金を借りる方法は?」
「生活福祉資金貸付制度の審査に通る方法を知りたい」
「生活福祉資金貸付制度の借り入れ手順は?」
失業や高齢などの理由で金融機関からお金を借りられない場合は、生活福祉資金貸付制度の利用を検討しましょう。
生活福祉資金貸付制度は、生活に困窮している世帯のサポートが目的の貸付制度なので、金融機関の審査に落ちた人でも借り入れができます。
しかし、実際にいくらまで借りられるのか、審査に通るのかどうか不安な部分もありますよね。
そこで本記事では、生活福祉資金貸付制度の審査基準や審査を通過する方法を解説します。
- 生活福祉資金貸付制度とは生活困窮者を対象にした国の貸付制度のこと
- 生活福祉資金貸付制度は5種類あり、連帯保証人がいれば無利子で借り入れ可能
- 安定した収入のある人、生活保護を受けている人、債務整理中の人は審査通過不可
- お金を借りるには住んでいる地区の市役所・社会福祉協議会に申請が必要
生活福祉資金貸付制度の審査に落ちる理由についても解説しているので、ぜひ最後までチェックしてください。
なお、人気のカードローンについては、カードローンおすすめランキングで解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

生活福祉資金貸付制度の審査基準は?融資の条件は生活再建が困難なこと
生活福祉資金貸付制度の審査に通過できるのは、「低所得者世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」のいずれかの条件を満たす人です。
それぞれ融資条件が細かく定められているので、事前確認が必要です。
- 低所得者世帯は住民税非課税程度が目安
- 障害者世帯は身体障害者手帳などの交付を受けた親族がいる世帯
- 高齢者世帯は65歳以上の家族や親族が対象
生活福祉資金貸付制度に申し込む前に、審査基準と融資の条件を確認しておきましょう。
低所得者世帯は住民税非課税程度が目安
失業などによって収入が低く、生計維持が困難な低所得者世帯であれば、生活を再建できるまで生活福祉資金貸付制度で借り入れできます。
低所得者世帯と認められる目安は、住民税が非課税となる程度です。ただし、実際にどの程度の世帯年収で非課税になるかは、居住している地域によって変わります。
生活福祉資金貸付制度の世帯年収目安がある自治体では、低所得世帯の基準が以下のように異なります。
| 都道府県 | 世帯年収の目安 |
|---|---|
| 北海道 | 一人世帯の場合年収360万円程度まで |
| 福島県 | 生活扶助基準額の1.7倍以下 |
| 京都府 | 生活保護基準の1.8倍以内 |
| 徳島県 | 生活扶助基準額の2.0倍以内 |
住民税が非課税の世帯ではなくても、自治体によっては生活福祉資金貸付制度の対象となるケースもあります。
住民税非課税の条件は各自治体のホームページに記載されているので、事前に確認しておきましょう。
障害者世帯は身体障害者手帳などの交付を受けた親族がいる世帯
障害者世帯も、生活福祉資金貸付制度の貸付対象になります。障害者世帯とは、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている家族と同居している世帯のことです。
障害者世帯には住民税非課税世帯などの条件はありませんが、自治体によっては所得基準があります。そのため、障害者世帯でも収入が多いと、地域によっては生活福祉資金貸付制度の審査に通りません。
また、生活福祉資金貸付制度の総合支援資金と障害年金は、それぞれ併用ができません。病気やケガが理由で働けない場合は、障害年金と生活福祉資金貸付制度のどちらか一方を選びましょう。
高齢者世帯は65歳以上の家族や親族が対象
65歳以上の人が属する高齢者世帯も、生活福祉資金貸付制度の利用が可能です。
高齢者世帯は年収条件が緩く、住民税非課税世帯ではなくても申請できます。年収に関係なく借り入れできるので、低所得者世帯よりも融資条件のハードルは低めです。
なお、土地や家屋などの不動産を保有している高齢者の場合、返済能力が高いと判断されて、審査に通りやすくなります。
生活福祉資金貸付制度の種類
生活福祉資金貸付制度には5つの種類があり、資金使途に合わせた借り入れが可能です。
- 総合支援資金は生活を立て直すまでの費用を借りられる
- 福祉資金なら介護や通院などにかかる費用を貸してもらえる
- 教育支援資金では入学金や授業料などを借りられる
- 不動産担保型生活資金では住宅を担保に生活費を借りられる
- 特例貸付(緊急小口資金)は一時的に生活が苦しいときの少額融資制度
どの種類も無利子または低金利で借り入れできるので、状況に適した種類を選びましょう。
総合支援資金は生活を立て直すまでの費用を借りられる
総合支援資金は、失業中や低所得などが原因で日常生活を送ることが難しい場合に、生活を立て直すまでの費用を借り入れできます。
総合支援資金には「生活支援費」「住宅入居費」「一時生活再建費」の3種類があり、いずれも連帯保証人を用意できる場合は無利子で借り入れが可能です。
| 資金の種類 | 用途 | 金利 | 貸付金額 | 返済(償還)期限 |
|---|---|---|---|---|
| 生活支援費 | 生活再建までに必要な生活費 | 連帯保証人あり:無利子 連帯保証人なし:1.5% | 2人以上の世帯:月20万円以内 単身世帯:月15万円以内 | 10年以内 |
| 住宅入居費 | 住宅を借りるために必要な敷金や礼金など | 連帯保証人あり:無利子 連帯保証人なし:1.5% | 40万円以内 | 10年以内 |
| 一時生活再建費 | 就職や転職に必要な技能習得にかかる費用、滞納している公共料金の支払いにかかる費用、債務整理をするためにかかる費用 | 連帯保証人あり:無利子 連帯保証人なし:1.5% | 60万円以内 | 10年以内 |
上記3種類の資金は併用も可能です。例えば食費や光熱費を支払うために生活支援費を借りながら、住宅入居費で家賃を補うこともできます。
福祉資金なら介護や通院などにかかる費用を貸してもらえる
福祉資金では、医療や介護にお金がかかる費用を借り入れできます。福祉資金という名目ですが、実際には冠婚葬祭や技能習得に必要な経費も借り入れが可能です。
なお、資金使途によって借りられる金額が以下のように異なります。
| 資金の目的 | 貸付上限額 | 据置期間 | 返済(償還)期限 |
|---|---|---|---|
| 生業を営むために必要な経費 | 460万円 | 6月 | 20年 |
| 技能習得に必要な経費 | 最大580万円 | 6月 | 8年 |
| 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 | 250万円 | 6月 | 7年 |
| 福祉用具等の購入に必要な経費 | 170万円 | 6月 | 8年 |
| 障害者用自動車の購入に必要な経費 | 250万円 | 6月 | 8年 |
| 負傷又は疾病の療養に必要な経費 | 最大230万円 | 6月 | 5年 |
| 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費 | 最大230万円 | 6月 | 5年 |
| 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | 150万円 | 6月 | 7年 |
| 冠婚葬祭に必要な経費 | 50万円 | 6月 | 3年 |
| 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 | 50万円 | 6月 | 3年 |
| 就職、技能習得等の支度に必要な経費 | 50万円 | 6月 | 3年 |
| その他日常生活上一時的に必要な経費 | 50万円 | 6月 | 3年 |
総合支援資金よりも高額な費用を借り入れできるのが特徴で、緊急でまとまったお金が必要になった場合に役立ちます。
また、連帯保証人を用意できる場合は無利子、連帯保証人がいない場合でも1.5%という低金利で借り入れできるため、高額な借り入れをしても利息の負担を軽減できます。
教育支援資金では入学金や授業料などを借りられる
教育支援資金は、高校や大学への入学や就学に関する費用が払えない場合に利用できる資金です。
教育支援資金には「教育支援費」と「就学支度費」があり、いずれも無利子で借り入れが可能です。
| 教育支援資金の種類 | 金利 | 貸付金額 | 据置期間 | 返済(償還)期限 |
|---|---|---|---|---|
| 教育支援費 | 無利子 | 高校:月3.5万円以内 高専:月6万円以内 短大:6万円以内 大学:月6.5万円以内 | 卒業後6ヶ月 | 据置期間終了後20年以内 |
| 就学支度費 | 無利子 | 50万円以内 | 卒業後6ヶ月 | 据置期間終了後20年以内 |
扶養している子供が複数人いる場合は、教育支援費と就学支度費の併用も可能です。そのため、子供が多い家庭でも教育費を十分に賄えます。
不動産担保型生活資金では住宅を担保に生活費を借りられる
不動産担保型生活資金は、65歳以上の高齢者が持っている住宅や土地を担保に生活費を借りられる制度です。
対象高齢者の死亡時または融資期間終了時に担保を処分して償還するため、お金を借りている間も引き続き住宅に住み続けることができます。
| 資金の種類 | 金利 | 貸付金額 |
|---|---|---|
| 不動産担保型生活資金 | 年3.0% | ・土地の評価額の70%程度 ・月30万円以内 |
| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 年3.0% | ・土地及び建物の評価額の70%程度 (集合住宅の場合は50%) ・生活扶助額の1.5倍以内 |
- 死亡時まで住み続ける住居である
- 単独所有している
- 抵当権等が設定されていない
なお、マンションなどの集合住宅や居住していない不動産は、不動産担保型生活資金の対象外になります。
特例貸付(緊急小口資金)は一時的に生活が苦しいときの少額融資制度
緊急でお金が必要な場合は、生活福祉資金貸付制度の「特例貸付(緊急小口資金)」を利用しましょう。
緊急小口資金は最大10万円までしか借りられませんが、融資スピードが早く、最短1週間で借り入れできます。
| 金利 | 無利子 |
|---|---|
| 貸付限度額 | 最大10万円 |
| 融資時間 | 最短1週間 |
少額資金ですが無利子なので、ブラックでどこからも借りれないときや、一時的に生活が苦しいときや緊急でお金が必要な場合に役立ちます。
生活福祉資金貸付制度の審査は厳しい?審査に落ちた理由を解説
生活福祉資金貸付制度は、生活が困窮している人を救済するための制度であるため、生活が困窮していないと判断されれば審査に落ちる可能性があります。
- 生活困窮者の救済が目的の制度のため安定収入のあると判断されると融資を断られる
- 生活保護世帯は原則対象外!社会福祉協議会に要相談
- 自己破産の手続き中または債務整理中は利用できない
- 無職は就労意欲がないと審査通過が厳しい
- 住居が確定していない場合は事前に生活困窮者住居確保給付金を申請する
生活福祉資金貸付制度の利用を検討している人は、審査落ちする原因がないか事前に確認しておきましょう。
生活困窮者の救済が目的の制度のため安定収入のあると判断されると融資を断られる
生活福祉資金貸付制度は、収入が少ない生活困窮者の救済を目的にした公的融資のため、安定した収入のある世帯は融資を拒否されます。
収入の基準は、生活保護法に基づく生活扶助基準の1.7倍程度です。例えば、生活扶助基準が10万円の場合、収入基準は17万円になります。世帯収入が17万円以下であれば、生活福祉資金貸付制度の審査通過は可能です。
なお、市区町村によっては収入制限が設けられているケースもあるので、各自治体のホームページで融資条件を確認しておきましょう。
収入が多い世帯は、消費者金融や銀行カードローンなど、民間の金融機関からお金を借りることをおすすめします。
生活保護世帯は原則対象外!社会福祉協議会に要相談
生活福祉資金貸付制度は、他の公的給付や公的融資制度と併用できません。生活保護や失業等給付金などの公的支援を受けている人は、生活福祉資金貸付制度の対象外です。
生活保護などの公的支援を受けていれば、日常生活に必要な資金は補われているので、生活福祉資金貸付制度の貸付対象である生活困窮者からは外れます。
すでに生活保護を受給している人が申請しようとしても、申し込み前に市役所や社会福祉協議会に他の方法を提案されます。
自己破産の手続き中または債務整理中は利用できない
自己破産の手続きや債務整理を行っている人は、生活福祉資金貸付制度を利用できません。
債務整理中は原則として金銭消費貸借契約ができないため、生活福祉資金貸付制度を利用しようとしても審査に通りません。
返済が困難な状況のなか、新たに借り入れすると、さらに生活が困窮する可能性があります。そのため、債務整理中は家計を見直し、弁護士に相談するのが得策です。
無職は就労意欲がないと審査通過が厳しい
生活福祉資金貸付制度は無職も利用は可能ですが、就労意欲がない人は審査に通りません。
もともと生活福祉資金貸付制度は生活再建を目的に設けられた制度のため、就職先を見つける努力をしていない無職の人は制度の趣旨から外れます。
働く意思がないといつまでも就職先が決まらず、借りたお金を返済できません。そのため、無職の人が生活福祉資金貸付制度を利用するには、就労するための努力を行動で示す必要があります。
- ハローワークに求職登録をする
- ハローワークで就労訓練を受ける
- 積極的に求人応募する
- 自治体から就労支援を受ける
働く意思があり、実際に努力していることを社会福祉協議会に強く伝えることができれば、生活福祉資金貸付制度の審査に通りやすくなります。
住居が確定していない場合は事前に生活困窮者住居確保給付金を申請する
生活福祉資金貸付制度は、住居が確定していないと申請を断られるケースがあります。
ホームレスやホテル暮らしなどで住居が確定していない場合は、事前に生活困窮者住居確保給付金を申請して、住居を確保しましょう。
市役所で生活福祉資金貸付制度の申請をしても、たいていの場合は住居確保給付金の申請を勧められます。
住居確保給付金は、3ヶ月間の家賃を保証してもらうことができ、返済義務はありません。 住居確保給付金によって住む場所を確保できれば、生活福祉資金貸付制度からの融資を受けられます。
住居確保給付金によって一定期間の家賃相当額を支給してもらえるだけでなく、生活福祉資金貸付制度で生活費もまかなえるため、生活再建に向けて大きく前進できるでしょう。
市役所でお金を借りる手順|居住地域の社会福祉協議会で申し込み手続きが可能
生活福祉資金貸付制度を利用するには、居住地域の社会福祉協議会で申し込み手続きが必要です。
社会福祉協議会は市役所の中に設置されているケースが多いので、まずは市役所に出向きましょう。
- 総合支援資金や緊急小口資金で借りる場合は自立相談支援機関での相談が必須
- 社会福祉協議会に申請書類などの必要書類を提出する
- 貸付決定になったら借用書を提出する|連帯借受人がいる場合は一緒に出向く必要がある
- 融資までの期間は最短でも1ヶ月!混雑すると時間がかかるので早めの申請が必要
生活福祉資金貸付制度は融資までに時間がかかるので、事前に手順を確認して、早めに申し込み手続きを行いましょう。
総合支援資金や緊急小口資金で借りる場合は自立相談支援機関での相談が必須
総合支援資金や緊急小口資金でお金を借りるには、事前に自立相談支援機関への相談が必要です。まずは、居住している市町村の自立相談支援機関窓口へ出向きましょう。
担当者から年収や支出などの家計状況を一通り聞かれたあと、融資が必要と判断されれば生活福祉資金貸付制度の申し込みが可能になります。
なお、福祉費や教育支援資金を利用する場合は、自立相談支援機関への事前相談は不要です。
社会福祉協議会に申請書類などの必要書類を提出する
自立相談支援機関で相談した後、社会福祉協議会に出向いて必要書類を提出しましょう。
必要書類に不備があると審査に通りません。必要書類は数が多いので、事前に提出すべき書類を確認しておきましょう。
- 借入申込書
- 本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・健康保険証など)
- 世帯員全員が記載された住民票(原則として1ヶ月以内に発行されたもの)
- 世帯収入の証明書(源泉徴収票・給料明細・確定申告書・収支内訳表など)
- 連帯保証人を立てた場合はその住民票の写しなど
- 連帯保証人の収入証明書
- 障害者手帳の写し(障害者として申請する場合)
- 生活保護世帯の場合は福祉事務所長の意見書
- 借金がある場合は総額・残額・返済状況がわかる資料
- 福祉費は各必要な書類(転居なら引越業者の見積もりなど)
申請する資金の種類によっては追加書類を求められるケースもあるので、事前に社会福祉協議会へ問い合わせて確認しておくと安心です。
なお、必要書類を提出する社会福祉協議会は市役所と同じ敷地内にありますが、一部の市町村では異なる場所に設置されている場合もあります。念のため、各自治体のホームページで場所を確認しておきましょう。
貸付決定になったら借用書を提出する|連帯借受人がいる場合は一緒に出向く必要がある
必要書類を提出した後、社会福祉協議会によって審査が行われ、審査に通過すると貸付決定通知書または不承認通知書が送付されます。
貸付決定通知書を受け取ったら、社会福祉協議会に借用書を提出しましょう。借用書を提出しないと、貸付資金が振り込まれません。
また、連帯借受人がいる場合は、借用書を社会福祉協議会に提出する際に一緒に出向く必要があります。
融資までの期間は最短でも1ヶ月!混雑すると時間がかかるので早めの申請が必要
申し込みから融資まで早くても1ヶ月程度、混雑している場合は2~3ヶ月かかるケースもあります。
生活福祉資金貸付制度の審査では、市区町村の社会福祉協議会で書類を確認した後に、都道府県の社会福祉協議会が再審査を行うため、 どうしても時間がかかります。
1ヶ月以内にお金が必要な場合は、緊急小口資金の利用を検討しましょう。借りられる金額は最大10万円ですが、最短1週間で借り入れが可能です。
ただし、申請しても利用できるとは限らず、審査落ちする可能性もあります。
融資まで1週間以上も待てない、すぐにお金が必要という場合は、即日融資可能なカードローンの利用を検討しましょう。